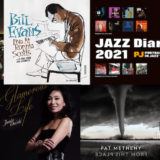結成から20年を超えて、我が国を代表するビッグ・バンドとして揺るぎない地位を確立している守屋純子オーケストラ。2月の渋谷区文化総合センター大和田 さくらホールを定期公演に位置づけ、毎回テーマを掲げたプログラムによって進化する姿を伝え続けており、継続的なオケの運営を含めて守屋がバンド・リーダーの力量を示すステージとして、すっかり定着している。守屋オケは2020年に新たなパフォーマンスの場所を求めて、東京丸の内・コットンクラブに進出。内外の著名ミュージシャンの出演によってブランドを確立するライヴ・レストランへの3年連続の公演は、コンサート・ホールに比べてステージと客席の距離感が近い環境が、従来のファンにも守屋オケの新鮮な魅力が体感できる機会として価値を生んでいる。2日間連続公演の2日目、セカンド・ステージを観た。

今回出演する17人編成の守屋オケは、今年2月の定期公演のメンバーから一部が入れ替わっており、同公演を鑑賞した私には新たなオケの魅力が発見できるのではないか、との期待感があった。メンバーがステージにスタンバイしたところで目を瞠った。前列のサックス・セクションの右隣にパーカッションの岡部洋一が位置している。これはホールと同じスペースが確保できないための措置だと思われるが、通例ではドラマーの右隣に配置されて縁の下の力持ち的な役割(元々守屋オケに打楽器奏者がいなかったところ、守屋の熱望によって岡部がリサイタルの正式メンバーになった)を担っていた経緯を踏まえれば、岡部のプレイが見逃せないとの鑑賞体勢になった。
オープニング曲の「チャールストン」はストライド奏法の完成者であり、ジャズ・ピアノの創始者として歴史にその名を刻むジェームス・P・ジョンソンが、チャールストン・ダンスを伴った1923年のレビュー『ランニング・ワイルド』のために作曲。今年2月の定期公演では3曲構成の<Jazz Dance Suite>の1曲目に選曲された。ソロ・ピアノの原曲を、トランペット~アルト~トロンボーン~バリトンの4人が短くリレーし、やがて4管の合奏となり、さらにバストロンボーンがソロを引き継いで、エンド・テーマに至る構成にアレンジ。約100年前の歴史的な楽曲がビッグ・バンド・ヴァージョンとして甦ったことが感慨深い。

やはり定期公演でも披露した「ソウルフル・ミスター・モーガン」は、50~60年代に最高の輝きを放ったモダン・ジャズ期の人気トランペッター、リー・モーガンに捧げた守屋のオリジナル曲で、ジェームス・ウィリアムス(p)がアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズ在籍中の80年代に提供した「ソウルフル・ミスター・ティモンズ」の曲名を拝借したもの。ピアノ&ベース・ユニゾンのイントロからリズミカルなテーマを経て、ソロ・リレーを展開する中では、バンド・メンバー中最年少で、定期公演には不参加だった佐瀬悠輔のトランペット・ソロが光った。続く「サウザンド・クレインズ」は亡き祖母を想って守屋が書いた『グルーヴィン・フォーワード』(2009年)収録曲。メロディアスなピアノのテーマで始まるスロー・ナンバーで、トランペットとフリューゲルホーンを持ち替えながら合奏するホーンズも印象的だった。
過去2回のコットンクラブ公演で新曲を発表した守屋が、今回用意したのは、フランス人ピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニ(1962~99)由来の「ミシェル」。2008年9月にフランスへ行った時、ペトルチアーニの曲にみんなでフランス語の歌詞をつけて歌った経験があり、パリの街がお洒落だと感じた思い出が作曲のインスピレーションになったという。哀愁味を帯びたボサテイストのテーマから、近藤(as)と駒野(tb)がリレーする進行で、ブラジル音楽を踏まえたピアノが、楽曲を貫いていたあたりは、ペトルチアーニの音楽性の一角を踏まえたものだと言える。

スタンダード・ナンバー「マイ・フェイヴァリット・シングス」が始まると、名前を呼び上げられることなくスペシャル・ゲストの土岐麻子がステージに歩んでくる。自身の『スタンダーズ』(2004年)収録曲のテーマを英語で歌うと、ホーンズの間奏を挟んで、ピアノとのデュオやソプラノ(近藤)とのやり取り、バンドと向き合ったスキャットで土岐の魅力を多角的にクローズアップ。ポップス畑出身の土岐は、ソロ・デビュ-となった同作をきっかけにジャズを自分の表現世界として拡大したキャリアを持っており、ジャズ・ミュージシャンとの共演も豊富だ。
歌い終えたところで、土岐は一言「いい夜ですね」。コロナ禍のため、ミュージシャンと観客がライヴ会場で接する機会が少なくなり、3年目の今年になってようやく回復傾向になってきた状況を踏まえての発言は、共感を呼んだ。土岐が守屋オケと共演するのは今回が2度目で、二人の結びつきは意外な印象もあるが、「(早稲田)大学の先輩ゆえの忠誠心(笑)」との説明で納得。岡部は同じサークルの先輩だという。
「懐かしい昭和の時代にタイムスリップして歌います」の前説で始まった「おてんばキキ」は、江利チエミが昭和31(1956)年の「NHK紅白歌合戦」で歌ったナンバーで、チエミ同様、1番の英語に続きスウィンギーな間奏を挟んで、2番を日本語で歌唱。エンディングでバンド・サウンドがピタリと決まり、選曲・歌唱・バンドが好ましく落着した。
「スウィングしなけりゃ意味ないね」は土岐の『スタンダーズ gift』(2005年)からの選曲で、同作では土岐英史(as)参加のカルテットとの共演による「スイングがなくちゃ意味がない」だった。作曲者のデューク・エリントンが自身の楽団の代表的なレパートリーとしたことを踏まえれば、守屋オケとの共演でこの曲を歌えるセッティングを土岐がどれほど嬉しく思っているのかは、想像に難くない。演奏はスローな合奏を皮切りに、通常テンポのテーマを歌唱。吉本章紘のテナー熱演と佐野聡のコントラストをつけたトロンボーンにスポットが当たり、さらにホーン・セクション&土岐のスキャットで楽曲のハイライトを演出した。

土岐が退いて、守屋オケは本編最終曲にチャールズ・ミンガス作曲の「ソング・ウィズ・オレンジ」を選んだ。59年録音の『ミンガス・ダイナスティ』収録曲はテンテットなので、その原曲を守屋がどのように拡大編成用にアレンジするのかが注目のポイント。岡崎好朗のトランペットを含むシャッフル・テーマ~ベース~5サックス~バンド合奏と進行し、各ホーンズが絡み合う展開に。今年で生誕100周年を迎えたベーシスト/バンド・リーダーへの、守屋流のトリビュートとなった。
アンコールに応えて登場した土岐は、演奏前のMCで観客の笑いを誘った。「(自分を含めたメンバー18人のうち)6人がスキンヘッドの男性、6人が女性、6人がスキンヘッド“じゃない”男性なので覚えやすい。今日は色々な意味で光をもらいました(笑)。楽しい!お客さんを前に歌うことは、最高に幸せです」。土岐だから許されるコメントであり、会場は多幸感に包まれた。最後に用意された「ギヴ・ミー・ザ・シンプル・ライフ」はエラ・フィッツジェラルド、カーメン・マクレエ、アニー・ロスが録音しているスタンダード・ナンバー。当夜のコラボレーションだからこそ実現したプログラムとして、特に土岐麻子ファンには大きなプレゼントになったのだった。

【Set List】
■①Charlston ②Soulful Mr. Morgan ③A Thousand Cranes ④Michel ⑤My FavoriteThings ⑥おてんばkiki ⑦It Don’t Mean A Thing ⑧Song With Orange [encore]Give Me The Simple Life
■守屋純子(p,cond) オーケストラ [佐久間勲、木幡光邦、佐瀬悠輔、岡崎好朗(tp) 佐野聡、東條あづさ、駒野逸美(tb) 山城純子(btb) 近藤和彦(as,ss)、緑川英徳(as)、岡崎正典、吉本章紘(ts)、佐々木はるか(bs) 安カ川大樹(b) 加納樹麻(ds) 岡部洋一(per)] 土岐麻子(vo)