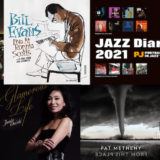米テキサス州ダラスを拠点に活動する女性ヴォーカリスト、ローラ・エインズワース。2011年にアルバム・デビューしたローラの少女期、CM制作会社勤務時代、プロのヴォーカリストとして活動する現在、さらに今後の予定について語ってもらった。
地元ダラスが音楽との関係において、特別な要素があるとすればそれは何ですか?
LA:素晴らしい質問ですね、地元について尋ねられたのは初めてだと思います。ダラスには多くの産業があって、中でもテレビ、ラジオ用のCM音楽やジングルのレコーディングが盛んです。私は「ジングル・ビジネス」で育ちました。父(ビリー・エインズワース)が数多くのCMでサックスやクラリネットを演奏していましたし、CMソングを歌うトップグループのリーダーでもあったので。私自身もカレッジ卒業後にTMプロダクションズというCM制作会社に勤め、ジングルを制作しました。そこで後に長い付き合いになるミュージシャン友達がたくさんでき、夫にも出逢いました。
もともとロサンゼルスで生活していた両親がダラスに移ったのは、コマーシャル・レコーディング業に携わって家族を養うためでした。父は夜にはソサイエティー・オーケストラの一員として仕事をしていて、トニー・ベネット(vo)やメル・トーメ(vo)といった大御所のバックや、当時まだ残っていたスウィング時代のミュージシャンと演奏していました。オールド・スタイルの高級サパークラブで演奏していましたね。火曜日はバンド・メンバーの家族はカバーチャージがなかったので、母がよく連れていってくれました。とても印象深い思い出です。
ダラス近郊のデントンについても話さないといけませんね。デントンにあるノーステキサス大学は世界初にして最高峰のジャズ研究学科を創設した学校です。同大学のワンオクロック・ラブ・バンドはグラミー賞ノミネート歴があります。私のバンドの中心メンバーのほとんどが、この学科で教授として教鞭をとっていますよ。

楽器演奏の経験について教えてください。
LA:私は音楽一家の中で育ちました。父はほぼすべての管楽器を見事に吹きこなせる神童でしたし、家族のほとんどはピアノを弾けて、祖母は10代の頃、女性バンドのラグタイム・ピアニストでした。私は独学でピアノと、楽譜を読めるようになり、高校生時代には合唱団のピアノを弾いていました。でも今は歌に集中することの方が好きですね。ベストなパフォーマンスを引き出してくれる、プロフェッショナルな素晴らしい演奏者たちがついていますから。
TMプロダクションズ時代にはCMジングルを制作したとのこと。作曲の才能はどのように身につけたのですか?
LA:そこで主にやっていたのは、出来上がっている音楽に歌詞をつけることでした。ラジオやテレビで流す、レストランチェーンやデパートなどのあらゆる業界のCMです。「フル・シング」と呼ばれるもので、60秒間の曲に、企業のスローガンを盛り込んだ歌詞をつけていました。ライブラリー全体が私の作品というぐらい、それこそ何千もの曲を書きましたね。
その経験はおそらく、今日私が作曲する際に曲(メロディ)から作り始めるのを好む理由になっていると思います。曲のアイデアと2、3行の歌詞ができたら、あとは作曲家にお任せします。曲全体が出来上がってきたら、私が歌詞をつけます。私の最初のオリジナル曲はCDにも収録した「The Man I Love Is Gone」で、これもそういう流れで作曲したものです。
それと、私は有名な曲のユーモラスなパロディソングを作るのも好きで、北米のラジオ番組用にたくさん作りました。以前「My Ship Has Sailed」というタイトルの一人芝居を書きましたが、劇中は愉快なパロディソングが満載です。
曲を書くのは大好きですが、忘れられた良曲を再発見することも私自身にとって同じぐらい重要ですね。オリジナル曲も書けるけれど、本当にたくさんの素晴らしい曲がこの世には存在していますから。たとえば1934年にアネット・ハンショウ(vo)がレコーディングして以来、誰も耳にしなかった曲をレコーディングして世に出すことできましたし。しょっちゅう古ぼけた曲を見つけては、「これを歌わなくちゃ!」と思っています。まさにそれが、私がやりたいことなのです。

プロの女優としてのキャリアが、現在のジャズ・ヴォーカル活動に良い影響を与えているとすれば、それは何ですか?
LA:演技の経験は、私の歌手活動に間違いなく良い影響を与えていますね。フランク・シナトラ(vo)が偉大な歌手になったのは、彼が俳優でもあったからだと言われています。優れた歌唱とは、単に自分の歌唱力を誇示することではなく、歌詞に込められた機微を表現することだと思っています。私はいつも、演劇の独白をイメージして歌に臨んでいます。
デビュー作『Keep It To Yourself』のEclectus Recordsはご自身で設立した会社ですか?
LA:そうです。Eclectus Recordsは個人レーベルで、夫でプロデューサーのパット・リーダーと所有しています。今や幸運なことに、テクノロジーやその他のリソースによって、インディペンデント・アーティストが簡単に作品をプレスし、流通させ、プロモーションできます。ただ、アルバムを発表していくアーティストとして活動を始めるには、依然として費用がかかります。高質なものを制作できるプロジェクトを組める資金ができるまで、起業を待ちました。最高なものを作れなければ世に出したくないので。
キャピトルやヴァーヴのような、大手レーベルが1950年代に発表した華々しいアルバムの数々と比べて遜色ない自身のアルバムを、イメージ戦略という意味でも作りたかったのです。適切なプロデューサー、演奏者、スタジオ、エンジニアが揃うまで待ちました。これからも私たちは進化していくでしょう。
デビュー作が高い評価を得た理由は何だと考えますか?
LA:『Keep It To Yourself』には、私が取り組んでいることや私のユニークさを示す、場所作りの目的がありました。最近のアメリカのジャズ・シンガーたちは、良質の魅力やウィットがあった1940年代や50年代のスター歌手たちに及んでいると思えません。だからこそ選曲、アレンジ方法、芸術的プレゼンテーションについて、熟考し、調査しました。完璧にできると思えるまで待ちましたが、結果的には賢明な動きでした。

第2作『Necessary Evil』からの「Out of This World」はインドで2枚の編集作に収録され、そのおかげで同地での公演が実現。同曲が編集作に収録されたことと、インド公演の裏話について教えてください。
LA:そのコンピレーション・シリーズは『Chill-Out Zone』といって、あちらから参加のお誘いがありました。「Out of This World」には、このシリーズにふさわしい、落ち着いた、霊妙な雰囲気があって、万国に通じると感じたのです。
インド公演は1月だったのですが、気温が32℃もあって、1月のダラスより暖かかったですね。最高の出来だったのは、ビーチにあるステージでのコンサート。インドの特定の地域に根強いジャズ・シーンがあることには驚きました。インド西海岸の都市ゴアにはすごく良いジャズ・バンドがいくつかあって、その中の一つは私のバックアップ・バンドに匹敵するほど素晴らしかった。彼らは、インド人奏者と、現地在住もしくは冬の間だけそこで過ごすイギリス人、ヨーロッパ人奏者という構成でした。
バンガロールにも何日か滞在して、そこでは著名インド人ミュージシャンで友人のリッキー・ケジと軽くレコーディングしました。彼は伝統音楽の複雑性や、それを創作するために必要な、研究レベルの話をしてくれました。彼のおもてなしもあって、宮殿から自然保護区まで、数日かけてすべてを見て回ることができましたよ。

『New Vintage』の収録曲「The Man I Love Is Gone」は唯一のあなたの作曲。作曲のインスピレーションと歌詞について教えてください。
LA:友人で才能豊かなギタリスト、ジョージ・ガリアルディと私は一緒に曲を作りたいとずっと話していて、あるときアイデアが浮かんだのです。「自分にはもう想いを抱いていない男と一緒に暮らしている女。彼の肉体はあっても、実体はない」というストーリー。その頃私はテレビドラマ「Mad Men」の大ファンでした。ドラマの登場人物のベティは、気まぐれな夫のドンに対してそのように感じていて、そこからインスピレーションを得ました。
“Didn’t pack his suitcaseDidn’t say ‘so long’
Didn’t wave and drive away
But the man I love is gone.”
私はこの最初のラインをジョージに渡して、ブルージーに仕上げてほしいと頼みました。彼が作ったメロディがすごく良かったので、残りの歌詞を完成させました。これは後日談なのですが、長年の冷め切った夫婦関係の末に離婚した友人が、この曲はまさに自分のことだと話してくれました。

『Top Shelf』について。3枚のオリジナル・アルバムに続く4枚目がそれらから選曲したベスト・アルバムというのは、出すタイミングが早いと思えるのですが。
LA:『Top Shelf』はここ西側、欧米で復活を遂げているアナログ市場を狙ってリリースしました。私のスタジオ・アルバムは今のところCDとダウンロード配信のみなので、私の音楽をアナログ愛好家に紹介するためにはこのコンピレーションがベストだと考えたのです。それに、私がやっているタイプの音楽はアナログであるべきだと思ったのもあって。私がインスパイアされたアーティストが作っていた曲は、ターンテーブルで再生されるものだから。これも経験の一つですね。特に日本ではアナログ人気が独自に発展しているようなので、制作して本当に良かったと思っています。
またCD版を出せば日本のジャズ・ファンが私の音楽に気軽に触れられるだろうと思っています。実際に今、CD版を制作し、日本でリリースする準備を進めています。
CD版について詳しく教えてください。
LA:『Top Shelf』CD版には新しいライナーノーツを入れ、流れの良い曲順に編集し直し、曲数を増やします。新しいライナーノーツとトラックリストは私の対日本代理人、デイヴィッド・ガスティンが担当しています。彼はアメリカで『This Is Vintage Now』というコンピレーション・シリーズの制作をしています。CD版には未発表曲、アーヴィング・バーリン・ヴァージョンの「You’d Be Surprised」を追加収録します。『Necessary Evil』の制作中に録音した曲なのですが、アルバムに入れられなかったので。
見本盤を有名ジャズ・プロデューサーに送ったところ、「パーフェクトなアルバムだ」と絶賛してくださって、本当に嬉しかったです。これまで日本のマーケットに向けて、とんでもない数のジャズ・アルバムをプロデュース、リイシューしてきた人がそう評価してくれるなんて。とはいえ、日本のジャズ・ファンにはアルバムを直接聴いて判断してもらいたいですね。
「Top Shelf」LPのために曲を選ぶ上でポリシーにしたことは?
LA:曲目を絞るのは本当に大変でした! ジグゾーパズルをやっているような感じでしたね。「Love For Sale」「Necessary Evil」「Out of This World」など、十分にスペースを確保しなければならない曲から選び始めました。また、バラエティに富んだ曲調とテンポにしたかった。たとえば「An Occasional Man」は楽しい曲調だし、将来もっとエキゾチカの音源をレコーディングしていきたいのもあって、絶対に外せませんでしたね。「My Foolish Heart」「Midnight Sun」など、個人的にお気に入りでも、長すぎるものは何曲かは外さなければなりませんでしたが。
お気に入りは人それぞれでしょうが、この選曲が「私」をよく表していると思います。CD版はアナログより曲数が増えるので、あなたのお気に入りが入っているかもしれませんね。

デビュー作から共演関係を続けているBrian Piperについて。ピアニスト&プロデューサーとしての彼の魅力とは?
LA:ブライアンとはそれ以前から組んでいて、先述の私のコメディ劇『My Ship Has Sailed』でも音楽監督とキーボーディストを担当してもらいました。私が最初のCD制作の準備をしていたころ、ブライアンはテキサスで最も需要の高いプロデューサー、キーボーディストでした。私たちは長い知り合いで、彼のご両親は私の父とも仕事していました。お父様はTMプロダクションズの作曲家・編曲家で、お母様はジングル歌手。ブライアンは私が何をやりたいかを正確にわかっているので、どんなに古い曲とクレイジーなアイデアを彼に持っていっても形にしてくれます。もし人々が私の音楽を「一段上」だと思ってくれるなら、それはほぼ彼のおかげでしょう。
同作は日本のリスナーに対する挨拶のようなアルバム。次のオリジナル・アルバムに関するアイデアは?
LA:次のプロジェクトは、オーディエンスのリクエストが主体となるでしょう。タイトルは『You Asked For It』になる予定です。聴きたいとリクエストされるのはある程度決まった曲たちなので、同じ曲を何度も繰り返して歌うことになりますね。ジュリー・ロンドンが最初にレコーディングした「Cry Me A River」はその一つ。リクエストが多い曲のうちのいくつかは、これまでに多くのアーティストによってレコーディングされているから、私自身は急がなくてもいいかと。でもやはり、多くの人々が聴きたいと言ってくれていますから、これまでのスタジオ・アルバム制作でやってきたのと同じように、アイデアを出しつつ、すでに世に出ているヴァージョンとは違ったアプローチでお届けしたいと考えています。

今後の予定について教えてください。
LA:『You Asked For It』とは別に「タイムトラベル」をコンセプトにしたアルバムのアイデアもあって、テーマに沿った曲をゆっくり集めているところです。もちろんその中のいくつかはとてもマイナーなものですよ。でも、今の一番の希望は日本でツアーすること。『ライヴ・イン・ジャパン』を作りたいですね。数年前まではそんなことは考えもしなかったけれど、近年はクレイジーな夢を実現させることができているし、今では絶対に可能だと思えるんです。