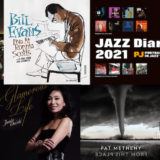1927年10月13日、米イリノイ州シカゴで生まれたアルトサックス奏者リー・コニッツが、節目の年齢を迎えた。有楽町~丸の内から渋谷へ会場を移した今年が初年度となった《第16回 東京JAZZ》では、9月3日のNHKホールに出演。「JAZZ100年プロジェクト」と題したステージは、1927年のオリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドによるジャズの初録音からの祝い年に、その歴史を1時間に凝縮した内容で、コニッツは“クール・ジャズ”の現役オリジネイターとして、自身が参加した49年のマイルス・デイヴィス『クールの誕生』収録曲「バップリシティ」を演奏した。欧米のジャズ誌を見ても、ジャズ100年は話題になっており、この日本独自の企画にコニッツをブッキングしたことは大きな収穫と言えるだろう。

コニッツは今も現役でライヴ活動を行っているわけだが、それだけにとどまらずレコーディング活動も衰えを知らずに継続しているのが驚異的だ。2010年代に入ってからのリリースに限っても、フローリアン・ウェバー(p)を擁したニュー・カルテットの『Live At The Village Vanguard』(Enja)、ブラッド・メルドー(p)+チャーリー・ヘイデン(b)+ポール・モチアン(ds)とのオールスターズ作『Live At Birdland』(ECM)、ビル・フリゼール(g)+ゲイリー・ピーコック(b)+ジョーイ・バロン(ds)と、こちらもオールスターズと呼ぶべき『Enfants Terribles: Live At The Blue Note』(Half Note)等がある。著名米国人がヨーロッパのレーベルでアルバムを制作することは、70年代から顕著になり、数多くのミュージシャンがその恩恵を受けた中で、コニッツは90年代にSteepleChaseとPhilologyを主舞台としてレコーディングの場を拡大した点で、突出した成果を挙げた。その背景として指摘できるのは、欧州の若い世代のミュージシャンと制作者の間にレジェンド・プレイヤーに対するリスペクトがあること。引っ張りだこなのだ。
私がジャズを聴き始めた77年からのリアルタイムの経験で言うと、新譜として接した初期の作品はチャールズ・ミンガス晩年の大編成作『Something Like A Bird』(77年、Atlantic)、ビル・エヴァンス(p)との再会作『Crosscurrents』(77年、Fantasy)あたりだったと思う。リーダー作ではアート・ペッパー(as)との共演が話題を呼んだ『High Jingo』(82年、Atlas)が印象深い。83年に大学を卒業して最初に就職したのが、同作を発売したレコード会社であった。
クール派の総帥レニー・トリスターノ(p)と共演した初リーダー作『Subconscious Lee』(49~50年、Prestige)、クール派の2大サックスが共演した『Lee Konitz With Warne Marsh』(55年、Atlantic)、コニッツ・トリオの最高傑作『Motion』(61年、Verve)と、まず聴くべきコニッツの入門作とは別に、デュオの代表作に挙げたいのが、ミシェル・ペトルチアーニ(1962~99)とのデュオ『Toot Sweet』(82年、Owl)だ。81年のセルフ・タイトル作で鮮烈なデビューを飾ったフレンチ・ピアニストは、たちまち80年代エヴァンス派のトップに躍り出る。それから間もないタイミングでリリースされた同作は、録音当時19歳のペトが経験豊富なベテランの胸を借りた構図が想像できる。ところが“ピアノの化身”は35歳もの年長者を前に、新人離れした親和性を醸し出したばかりでなく、逆にコニッツの新たな魅力を表現することにも貢献していて、その後、世界的に活躍する才人の初期記録として価値が高い。手元にある“新譜”として購入したレコードは、裏ジャケットにディストリビューターだった「DIW」の金色のシールが貼り付けられている。