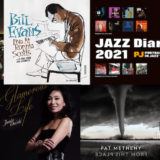1980年代から90年代初頭に晩年のスタン・ゲッツを助演して名声を獲得。その後は名匠から巨匠への道を歩み続けているピアニスト、ケニー・バロンが、北川潔(b)+ジョナサン・ブレイク(ds)とのトリオで来日した。その折に、トリオやマルグリュー・ミラーとの最新共演作について話を聞いた。
現在のトリオを結成したのはいつですか?
KB:キヨシとの共演歴は、もう25年になります。ジョナサンとは20年ですね。私のオリジナル・トリオはベン・ライリー(ds)とレイ・ドラモンド(b)。レイが教育活動のため、カリフォルニアへ移り、ベンは健康問題を抱えていました。ベン+キヨシとのトリオでしばらく活動。実は私の妻がジョナサンを推薦してくれたのです。どこかの会場で彼の演奏を聴いたのがきっかけでした。そういうわけでこのトリオは結成20年になります。
現在のトリオは歴代で最長ですか?
KB:はい、そうです。
2016年発売の『Book of Intuition』(Impulse)がトリオのデビュー作。結成以来、そこまで時間がかかった理由は?
KB:どこからも制作の依頼がなかったからですよ(笑)。このアルバムはユニバーサルミュージックとプロデューサーのジャン=フィリップ・アラールが提案してくれて、実現しました。

北川+ブレイクとのトリオの特別なところとは?
KB:彼らと共演していて、私自身がとても心地良く感じられるのです。ジョナサンは私にリズム面でとても挑戦的な刺激を与えてくれます。変化球を投げてくるんですよ。だから私は常に注意深くなければなりません。これは私にとってのチャレンジであり、好きなことです。
2日前のセットリストでは「ナイトフォール」が唯一のアルバム収録曲でした。
KB:これは作曲者のチャーリー・ヘイデン(b)とよく演奏した曲です。とても美しい曲で、私は恋に落ちたほどでした。でもレコーディングはしていなかったので、このアルバムにふさわしいと思って選曲したのです。
今回の公演ではアブドゥーラ・イブラヒム(p)に捧げた自作曲「ソング・フォー・アブドゥーラ」を独奏されました。
KB:アブドゥーラがNYに住んでいた時、“スイートベイジル”というジャズ・クラブがありました。彼はそこで毎週月曜日の夜に、カルロス・ワード(as)とのデュオで出演。彼らの音楽は讃美歌のように美しくて、まるで教会で聴いているような気分でした。そのメロディとコードはそれほど複雑ではなく、音楽のエッセンスを自分なりに掴みたいと考えて作曲しました。
この曲をライヴで演奏する時は、いつもソロですか?
KB:デュオで演奏したこともあります。最初のパートナーはジョン・スタブルフィールド(ts)でした。寺久保エレナ(as)ともこの曲で共演していますよ。NYの“ディジーズ・クラブ・コカコーラ”に私のトリオで出演した時や、最近ではカリフォルニアでも彼女とデュオで演奏しました。

今年はマルグリュー・ミラー(p)とのデュオ作『The Art Of The Piano Duo』(2005、2011年録音、Groovin’ High) がリリースされました。
KB:最初にデュオで共演したのはNYの“ブラッドレイズ”。とても良い感触を抱きました。次にベースとドラムのリズム・セクションが入った編成で、2005年にヨーロッパをツアー。スペイン・バルセロナのプロモーターがマルグリューとのデュオ・ツアーを企画して、フランスのマルシアックやスイスのジュネーブ等を巡演しました。
マルグリューが他界した前年の2012年が、最後のデュオ・ツアーになりました。
KB:マルグリューとのツアーは本当に素晴らしいものでした。私たちは音楽について打ち合わせをしたことは一度もありません。ピアノに向かって座り、演奏する。ただそれだけです。彼が何かの曲を弾き始め、私も同じように弾き始める。言葉はいらないのです。演奏がどのような方向に進んでいくのかは、二人とも分かりません。だから常に新鮮な気持ちで演奏し続けることができました。

これまでにスタン・ゲッツ(ts) 、ジョルジュ・ロベール(as)、チャーリー・ヘイデン、デイヴ・ホランド、バスター・ウィリアムス、レッド・ミッチェル、ハーヴィー・S(b)、ジョー・ロック、マーク・シャーマン(vib)、ミノ・シネル(per)、レジーナ・カーター(vln)とのデュオ作を発表。ピアニストとのデュオ作はありましたか?
KB:ありますよ。78年に日本のレーベルDenonが企画・制作したトミー・フラナガン(p)との『Together』です。トミーとはこのレコーディング以前に共演したことがなく、NYのスタジオが初共演の場所になりました。トミーは私が中学生時代からのアイドルです。マルグリューとの『The Art Of The Piano Duo』はそれ以来のピアニストとのデュオ作になりますね。
何故約40年もの間、ピアノ・デュオを制作していなかったのですか?
KB:それはただ単に、作ろうという気持ちにならなかったからです。マルグリューとツアーをして初めて、制作したいと思いました。

初出が92年の2枚組で、2009年に7枚組の『The Complete Recordings』がリリースされたスタン・ゲッツとの『People Time』(Verve)を除けば、3枚組の同作は例外的ですね。
KB:提案したのは私ではありませんよ。レコーディングの素材が多かったので、スイスのプロデューサー、ジャック・モヤール(Jacques Muyal)が3枚組を提案したのです。私はそのアイデアに賛成しました。
マルグリューの魅力を教えてください。
KB:すべてですよ(笑)。まずピアノのタッチが素晴らしい。そしてテクニックとハーモニック・コンセプトも。彼の演奏を聴いて、学んだ部分もたくさんあります。デュオ・ツアーで彼のソロ曲の時は、ステージの袖でじっくりとその演奏に耳を傾けました。
セロニアス・モンクの楽曲を好んで演奏されています。その魅力とは
KB:何でしょうね。普通じゃなくて、ユニークで、しかもハーモニーが挑戦的。シンプルなように思えて、実はそうではない。モンクの曲は演奏してみると楽しいんですよ。
モンクの楽曲を演奏する時に、彼の作曲家としての哲学を感じますか?
KB:モンクが考えた哲学についてはわかりませんが、私が演奏する時に意識しているのはモンクの真似をしないことです。モンクは唯一無二だからです。私が以前活動していたグループ“スフィア”では、私たち自身のコンセプトでモンクの楽曲を取り上げました。モンクの真似をするだけなら、それは愚かなことですよ。英語には“tongue in cheek”という言葉があって、「ユーモラスなやり方で」を意味します。

まだ実現していない夢のプロジェクトがあれば教えてください。
KB:ウィズ・ストリングスのバラード集に取り組んでみたいですね。ピアノ+ストリングスではなく、ピアノ・トリオ+ストリングス。ビル・エヴァンス(p)の『Bill Evans Trio With The Symphony Orchestra』(65年、Verve)が、私のイメージに近い。クラウス・オガーマン(arr,cond)がショパンやフォーレなどクラシックの楽曲の素晴らしいアレンジを手掛けた作品です。私の作品ならバラードのスタンダード・ナンバーで構成するでしょう。
アルバムで初共演したい人はいますか?
KB:たくさんいますよ。アジア系でNY在住のジェン・シュー(vo)。彼女とは何度か会ったことがあります。ヴォーカリストでありダンサーでもあるので、伝統的な音楽にはならないでしょうね。自分の境界を広げるためにも、彼女との共演にとても興味があります。
境界を広げると言えば、90年代にGitanesやVerveの作品を手掛けたプロデューサーのジャン=フィリップ・アラールも大きな貢献者ではありませんか?
KB:ジャン=フィリップは私が最も好きなプロデューサーの一人です。ロイ・ヘインズ(ds)+チャーリー・ヘイデン(b)とのトリオ作『Wanton Spirit』(94年、Gitanes)は彼のアイデアで生まれたものです。彼から提案された時に、私も賛同しました。ロイとは私が1961年にNYへ移った時に、初めて共演。レコーディングの時点でチャーリーとも何度か共演していました。同作のように通常とはまったく違うコンセプトのアルバムでは、必然的に異なるやり方で演奏することになります。私はそれを良いことだと思っています。

(2019年10月31日、丸の内コットンクラブで取材)