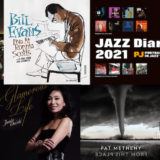改めて詳述するまでもないと思うが、キース・ジャレットが過去30年間に行ってきた音楽活動が、類例を見ないほど多岐に渡り、ジャズの歴史を塗り替えてきたことは明らかである。1970年代の活動を3つの柱に集約した時、ソロ・コンサート、ヨーロピアン・カルテットと並ぶ最も重要な表現装置がアメリカン・カルテットだった。キース+デューイ・レッドマン+チャーリー・ヘイデン+ポール・モチアンで結成されたアメリカン・カルテットは、73年2月のNY“ヴィレッジ・ヴァンガード”ライヴ『フォート・ヤウ』で正式なレコーディング活動をスタートさせ、76年10月の『バイアブルー/バップ・ビー』セッションまで、約4年間の歴史を築いて幕を閉じた。その間10枚のアルバムを制作し、2度の来日公演を実現させるなど、決して長くない期間の中で濃密な音楽的成果を成し遂げたのである。
ここで彼らにとって最後の年にあたる76年の動きを、キースを中心に再確認しておきたい。一目でわかりやすくするため、最初に時系列で箇条書きにする。
- 3月18日:チャーリー・ヘイデン『クロースネス』に参加
- 4月:カルテット作『ザ・サヴァイヴァーズ・スウィート』(『残氓』)録音
- 5月:ソロ・ピアノ作『ステアケース』録音
- 5月:カルテット・ライヴ『アイズ・オブ・ザ・ハート』(『心の瞳』)録音
- 9月:オルガン独奏作『賛歌』録音
- 10月14~16日:カルテット作『バイアブルー』『バップ・ビー』録音
- 11月5~18日:ソロ・コンサート作『サンベア・コンサート』録音
まず注目すべきは、Impulse所属のアメリカン・カルテットが、ソロを始めとするキース個人の契約レーベルであるECMで、2枚のアルバムを制作していることだ。75年12月に行われた『シェイズ/ミステリーズ』セッションの4ヵ月後、彼らは『残氓』のレコーディングのためドイツの“Tonstudio Bauer”に入る。それぞれLPの片面を占める「ビギニング」、「コンクルージョン」と題した組曲は、前半でソプラノ、テナー、チェレスタ、ベース、パーカッションが有機的に結びつきながら、神秘的/霊的な緊張感を創出し、後半になると冒頭からレッドマンのフリー・ブローイングが爆発。カルテットは即興的な一体感を持続しながら、劇的なクライマックスへと疾駆する。アメリカン・カルテットの音楽的営為のまさに集大成と呼ぶべき作品であり、70年代のすべてのジャズを通じても、稀にみる驚くべき成果の記録なのだ。ECM的特性が何らかの作用をカルテットに及ぼし、それ以前のImpulse録音では表現され得なかったカルテットの凄さを生んだのか。確かに後半の緊張感には目をみはるものがあり、ここまでの高みに上り詰めた後、一体彼らはどこへ向かうのだろうか、との不安さえよぎるほどの完成度の高さを見せつけてくれた。ところがカルテットは、ここで終わらなかった。翌月に行われたツアーでのオーストリア・ブレゲンツにおけるステージ。ライヴ・アルバム『アイズ・オブ・ザ・ハート』としてリリースされた演奏は、キースがカルテット内部で問題を抱えていたことを、浮き彫りにする。イアン・カー著『キース・ジャレット――人と音楽』(91年)の中で、キースはこの時の様子を次のように語っている。
「ぼくらは〈サヴァイヴァーズ・スウィート〉を演奏していた。この曲では、メンバーがところどころ入れ替わって演奏するようになっている。あるところではデューイがメロディを受け持ち、それからしばらく休んで、またソロを受け持つ。ところがデューイは最初のメロディを吹き終わると、ステージから引っ込んでしまったんだ。ぼくはリードでも交換しているんだろうと思った。そのうちに出番になっても、彼はステージに戻ってこなかった…。それで、ぼくは彼がステージに戻るきっかけをつかめるようにと、何とかして長いヴァンプを演奏しようと躍起になっていた…。後からぼくはデューイに言った。『ところで、何でステージから消えてしまったんだい?』。彼の返事は『ああ、ワインを一杯やりに行ったのさ』。クラブで演奏していたわけじゃないんだぜ!」。
同作の2枚組LPは第4面に演奏が収録されていない。これもまた極めて異例な形である。キースがECMプロデューサー、マンフレート・アイヒャーに同作の発表を許諾したのは、コンサートから2年後のことだったが、いわくつきのライヴを敢えて作品化したECMの意図とは何だったのだろうか。いずれにしても彼らがピークを極め、直後崩壊への道を明らかにしたことで、アメリカン・カルテットは実質的にユニットとしての終焉を迎えつつあった。先に触れたキースの伝記でも、イアン・カーは『心の瞳』がカルテット最後のアルバムだと記しており、それが定説となっていた。同著所収のディスコグラフィーでは、『バイアブルー』が“75年末か76年初め”とされ、ECMの2枚=アメリカン・カルテット最期の記録を裏付けた。その定説を覆したのが、97年発売の4CD『ミステリーズ~ザ・インパルス・イヤーズ1975~1976』。未発表音源も収録したこのBOXセットによって、『バイアブルー』と『バップ・ビー』は76年10月14~16日の同日セッションであると判明したのだ。これはつまり『心の瞳』の5ヵ月後に、アメリカン・カルテットのラスト・レコーディングが行われていたことを意味する。関連作の国内発売を確認しておく。
- 77年10月『残氓』、『バイアブルー』
- 78年3月『マイ・ソング』
- 78年6月『バップ・ビー』
- 78年9月『サンベア・コンサート』
- 79年6月『心の瞳』
リリース・スケジュールだけを見れば、当時のファンが『心の瞳』をカルテット最期の作品だと受け取ったとしても不思議ではない。またぼくの記憶によれば、『バップ・ビー』に対するアルバム評は、「未発表音源の落穂拾い」的ニュアンスだった。それもこれも初出時に録音年月日をクレジットしなかったことに原因がある。それにしても不思議に思う。ここには『残氓』で壮絶な演奏を繰り広げたカルテットの姿はなく、どこか奇妙な明るささえ感じられるのだ。この謎を解くためには、まだしばらく時間が必要なのか…。
レッドマン作曲の「ムシ・ムシ」はアップ・ダウンの激しさと、コルトレーン・ライクなテナーが“フリー・バップ”調で、インパクトが強い。バップとモンクのエッセンスを注入したキースが、モチアンの独特にスウィングするドラミングに歓喜の声を漏らす場面は、キースの働きかけでレッドマンが作ったナンバーの素晴らしさに対する喜びも重なったのだろう。「サイレンス」は『マジコ』(ECM)、『エチュード』『サイレンス』(Soul Note)といったリーダー作で再演を重ねたヘイデンの代表曲。タイトル通りショパンの「ノクターン」を彷彿させる、静かで落ち着いた曲調だ。本作中キース唯一の自作曲「バップ・ビーはチャーリー・パーカーの「コンファメーション」のコード進行をヒントにしたようなナンバー。“ビ・バップ”を逆さにしたネーミングとは裏腹に、スタイルは至って正統なバップ調だ。この時期にレッドマン抜きのトリオで、オリジナルのバップ曲を採り上げている事実は、非常に重要だ。キースは94年の『アット・ザ・ブルーノート』以降、トリオのレパートリーとしてこの曲を甦らせている。「ピラミッズ・ムーヴィング」(初出国内盤邦題「動くピラミッド」)は一転して、奇妙な楽想が怪しげな世界へと誘う。キースはピアノの弦をかき鳴らす内部演奏に終始。レッドマンがミュゼットを手にすると大抵こうした展開になるのも、アメリカン・カルテットの十八番だ。「ガッタ・ゲット・サム・スリープ」は「ムシ・ムシ」のヴァリエーションとも言えるアップ・ナンバー。「ブラックベリー・ウィンター」のようなスタンダード曲を採用したのも、本作の新機軸。アレック・ワイルダーの作品にあって、比較的知名度の低いこの曲を発掘したあたり、スタンダーズ・トリオのルーツを探る意味でも興味深い。「ポケットフル・オブ・チェリー」(初出国内盤邦題「ポケット一杯のさくらんぼ」)はヘイデン曲だが、どこかレッドマンに通じる作風。エネルギッシュなテナー・ソロを受けて、キースのソプラノも奮闘する。