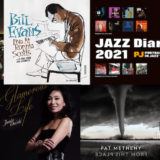2017年リリースの最新ソロ作『オープン・ブック』が、米グラミー賞《ベスト・ジャズ・インストゥルメンタル・アルバム》と《ベスト・インプロヴァイズド・ジャズ・ソロ》の2部門にノミネートされ、母国での高い評価を裏付けたフレッド・ハーシュが、2015年11月以来となる来日ソロ・ステージのため、丸の内コットンクラブに出演。3日間連続公演の初日、ファースト・セットを観た。

ステージに登場すると、いつものようにピアノの隣に位置して、深々と頭を下げる。1曲目はジョージ&アイラ・ガーシュウィンが書いた「エンブレイサブル・ユー」。ソロ作『アット・メイベック』(93年、Concord)の冒頭を飾ったスタンダード・ナンバーは、スロー・テンポの演奏が定石のところ、リズム・フィールのある設定に。右手のメロディ・ラインに対して、左手がそれを支えたり、独自の旋律を紡ぐ動きを見せることによって、両者が合体した音楽的生命力の源となる。両手から生まれる音の糸が複雑に絡み合って、美しいタペストリーを制作しているイメージだ。エンド・テーマで心地良く落着。

最初のMCで「新しいピアノ」と言ったのは、開店以来の歴史を刻んできたスタインウェイのピアノが昨年末に水害のため新調を余儀なくされて、器種の異なるスタインウェイを導入したことによる。2曲続けての演奏をアナウンスして始まったのは、最新作に収録のハーシュの自作曲「プレインソング」。音数が少ない静かな雰囲気の演奏は、食器の音を立てるのもはばかれるほど。咳をする客は一人もいない。全員が音楽に集中している。しばらくすると突然、視界がぱっと開かれるような瞬間が訪れた。右手の速いパッセージと左手の対比的なラインが、絶妙に融合する。メドレーのように始まっていたのは、ハーシュ作曲の「ハヴァナ」だった。トリオ作『アライヴ・アット・ザ・ヴァンガード』(2012年)のヴァージョンを踏まえると、ベーシストが弾いていたラインをハーシュが左手で担って、一人でトリオに匹敵する音場を作ろうとしたことがわかる。音の渦を作りながら進める演奏が、どのように落着するのだろうか?、の疑問は、ピタリと停止して観客も納得。

続いてはアントニオ・カルロス・ジョビンを2曲。長年ブラジル音楽を研究し、その成果を2009年リリースの『プレイズ・ジョビン』で知らしめたハーシュは、同作からの「もう喧嘩はしない」をジョビン曲らしいリズム・パターンでスタート。右手のジャジーなメロディ・ラインと、左手の変化するベース・パターンが、ブラジル人ピアニストとは異なるハーシュの個性を浮き彫りにする。やはり同作からの「マリアへ愛の歌を」は、終始静かなムードを保つ演奏だった。
ハーシュは2001年に現在までのキャリアで唯一最大の3枚組作『ソングス・ウィザウト・ワーズ』を発表。コール・ポーター集のDisc-3からの「ドント・フェンス・イン・ミー」は、シンプルなメロディの原曲をシンプルに弾くことに腐心する姿が伝わって来た。エンディングがチャーミング。
ハーシュがポップスをレパートリーに加えて、ライヴで繰り返し演奏するようになったのは、それほど前のことではないと思う。「青春の光と影」は2015年発表の『ソロ』収録曲で、ジョニ・ミッチェル初期の代表曲。まずシンプルにテーマを弾くと、ソロ・パートでは別の曲のように展開して楽曲の可能性を引き出す。音圧を上げて劇的なピークに至り、静かに美しく締め括る構成は、まさにプロの技だ。
セロニアス・モンクのナンバーをライヴで常とするハーシュは、本編の最後にソロ作『セロニアス』(98年発表)から「アスク・ミー・ナウ」を選曲。他のモンク曲の断片をちりばめながら、モンク・フレイヴァーを演出するあたりに、巨星への敬愛が重なった。

アンコールは最新作の最終曲でもある「アンド・ソー・イット・ゴーズ」。ビリー・ジョエルが『ストーム・フロント』(89年)の最後にピアノの弾き語りで演じたこの曲は、聖歌にも通じる神聖な曲調ゆえに米国のハイスクールや合唱団でも取り上げられていて、ハーシュもその楽想に沿ってしめやかに綴った。
当夜の演奏は総じて、音の連なりが自然体で、ハーシュに迷いがない印象。『オープン・ブック』の内ジャケットに記された本人のコメントに、符合する次の一節がある。「経験を重ねてきたことで、私はただシンプルにフレーズからフレーズへと演奏することによって得られる自由に、とても心地良さを感じているのです」。