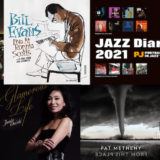「私にとってそれはクラシックの音楽家が初めてカーネギー・ホールに出演するのと同じことを意味していました。世界最高のジャズ・クラブなのですから」。
1935年創業のニューヨーク“ヴィレッジ・ヴァンガード”はソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスを始め、数々のライヴ作を生んでジャズの歴史を作ってきた名店。ピアニストのフレッド・ハーシュはトリオの『ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(2002年)、『アライヴ・アット・ザ・ヴァンガード』(2012年)、『サンデイ・ナイト・アット・ザ・ヴァンガード』(2016年)、ソロの『アローン・アット・ザ・ヴァンガード』(2010年)を、ジャズのメッカでレコーディングしてきた。2010年代に限れば、最も作品数の多いミュージシャンと言っていいだろう。
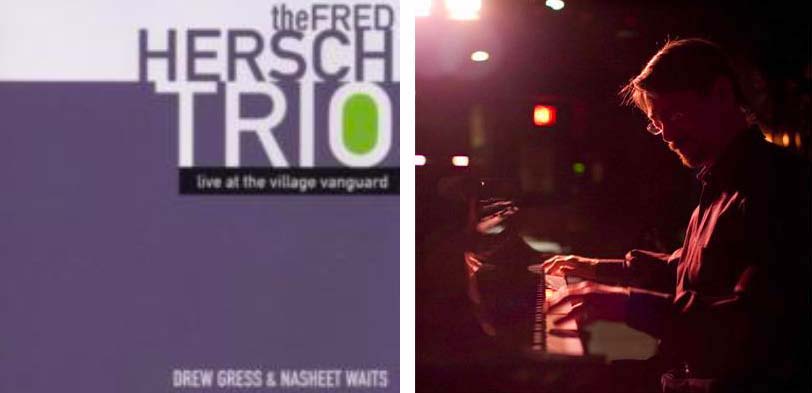
79年以来サイドマンとしてジョー・ヘンダーソン、アート・ファーマー、リー・コニッツ、ロン・カーター、アル・フォスターのリーダー・バンドで同店に出演。エンリコ・ピエラヌンツィPJBトリオのデビュー作『ニュー・ランズ』と同じ84年にマーク・ジョンソン(b)+ジョーイ・バロン(ds)と録音した初リーダー作『ホライゾン』(Concord)を皮切りに、チャーリー・ヘイデン(b)に交代した『サラバンド』(86年、Sunnyside)、ソロ・ピアノ・ライヴのシリーズ『アット・メイベック』(93年、Concord)等のリーダー作を通じて知名度と評価を高めたこともあって、同店からオールスターズによる自身のリーダー・バンドでの出演もオファーされた。しかしハーシュはそれを快諾するどころか、時期尚早と判断して固辞。その時だけの企画バンドではなく、あくまでも自分のワーキング・バンドが出演できるレヴェルに達したらと、そのタイミングを慎重に計っていたというから、これはハーシュが恋焦がれる“ヴァンガード愛”と言うほかない。

Photo by Martin Zeman
愛の実現は97年7月。ドリュー・グレス(b)+トム・レイニー(ds)とのトリオ。91年に始動した彼らは、93年に『ダンシング・イン・ザ・ダーク』と94年に『プレイズ』(以上Chesky)を発表しており、デイヴ・ダグラス(tp)、リッチ・ペリー(ts)が参加した95年の『ポイント・イン・タイム』(Enja)、ストリング・オーケストラ参加の96年作『パッション・フラワー』(Nonesuch)と着実に実績を積み重ねていて、初めてのリーダー・トリオ@ヴァンガードを迎えたのだった。
本作はアルバム化が前提ではなく、記録のために録音された音源だったが、最近それを聴き直したハーシュがサウンドと演奏のクオリティの高さに驚いたことで、世に出た経緯がある。このあたりはキース・ジャレットの事例とも重なって興味深い。つまりECM=プロデューサー、マンフレート・アイヒャーと濃密な信頼関係を築いているがゆえにリリース・スケジュールが決められるキースに似た関係が、2002年発表作から数えて本作が9枚目となるハーシュとPalmetto Recordsの間に生まれていると想像できるのだ。自分が安定的に作品を発表できる場所を確保していることが、ハーシュの好調なリリースの背景にあることは間違いない。

コール・ポーター作曲のオープニング曲「イージー・トゥ・ラヴ」は、アップテンポとワルツを組み合わせたテーマでスタート。先発ソロのハーシュは途中でテンポ・アップして観客を惹きつけたりワルツにしたりと、テーマで示したアレンジを展開させる。エンド・テーマの後にピアノとベースがやり取りするアウトロを入れたのも、有名曲に独自の価値を加えた点でいい。ハーシュ・トリオは2001年発表作『ソングス・ウィザウト・ワーズ』(Nonesuch)にこの曲を収録しており、ライヴのレパートリーとしてこのテーマ・アレンジを練り上げていたことがわかる。
「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」は『ダンシング・イン・ザ・ダーク』収録曲。同作では最初からトリオによるバラード演奏で、それは最後まで変わらなかったのに対して、ここではピアノ独奏のイントロから始まり、後半に進むとミディアム・テンポに乗ったトリオが熱気を帯びている。作詞バート・カルマー、作曲ハリー・ルビーの「スリー・リトル・ワーズ」は、30年にリズム・ボーイズの歌唱でデューク・エリントン楽団が初録音。注目すべきはレイニーのドラミングで、テーマにブラシを使用すると、ピアノ・ソロのバックではブラシの柄の部分でシンバルを叩いたり、ハイハットを巧みに開閉したり、途中でスティックに持ち替えたりと、プレイが多彩。ピアノとドラムの小節交換を経て、エンディングはピタリと落着する。ハーシュがジョン・エイベア(b)+エリック・マクファーソン(b)とのトリオで2011年に発表した『エヴリバディーズ・ソング・バット・マイ・オウン』(Venus)のヴァージョンは、終始ブラシがリズムを刻み、やはりピタリと終止していた。ちなみに曲名の“three little words”とは“I love you”の意味。

ハーシュの自作曲「エヴァネッセンス」は敬愛するピアニストへのトリビュート作『ビル・エヴァンスに捧げる』(『Evanessence: A Tribute to Bill Evans』Jazz City、90年発表)が初演で、同作での邦題は「エヴァンスの肖像」だった。曲名がエヴァンス作『Quintessence』(Fantasy)を連想させるこの曲は、ピアノ&ベースのユニゾンでテーマを演じる。「ビルが気に入ってくれるような曲だと思いたい」とのハーシュの初演コメントを踏まえると、エヴァンスの「T.T.T.」に通じる曲調から深い想いが感じられる。
「アンドリュー・ジョン」は作曲者のドリュー・グレスが本作の翌月に制作した自身のリーダー作『ヘイデイ』(Soul Note)が初演。その後2006年録音のハーシュ・トリオ作『ナイト&ザ・ミュージック』(グレス、ナシート・ウェイツ[ds])に収録された。つまりグレスが自身の在籍するハーシュ・トリオのために提供した楽曲は、少なくとも9年前からハーシュが演奏していた、ということだ。ピアノがメインの間、テンポ・ルバートで進む。
ハリー・ウォーレン作曲の「アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー」は、『ビル・エヴァンスに捧げる』収録曲。同作のライナーノーツでハーシュは『エクスプロレーションズ』(Riverside)のエヴァンス・ヴァージョンを聴かずに演奏したと語っているが、本当だろうか。スコット・ラファロ(b)+ポール・モチアン(ds)とのエヴァンス・ファースト・トリオが59年から61年に録音した公式作は、同作を含めてわずか4枚。ハーシュの初演はアブストラクトな曲調が偶然、エヴァンス・ヴァージョンと同じだった。ここではピアノ主導でリズミカルに進み、4分30秒になってようやくテーマ・メロディが顔を出す構成である。
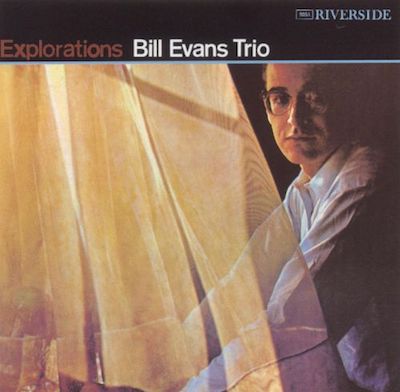
「スワンプ・サング」は前出の2002年ライヴ作に収録されることになるハーシュの自作曲。サザン・ロックで使われる「スワンプ」はジャズでは馴染みが薄い言葉だが、演奏を聴けばなるほどと頷けるブルージーな曲調。アーシーでラフなピアノ演奏はハーシュの別の顔を映し出している。
最終曲のスタンダード「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ」は、ハーシュとジェイ・クレイトン(vo)のデュオ作『ビューティフル・ラヴ』(Sunnyside、95年発表)の再演。通例はバラードのところ、ここではアップテンポの設定で、減速と加速で進行。ジャズを知る観客ならハッとするアレンジで、インパクトを与える。
ハーシュが21年前の演奏に価値を見出して世に出す初の試み。キャピトル・スタジオの仕事で知られる名匠マルコム・アディが録音を手掛けたことにも感謝したい発掘作である。